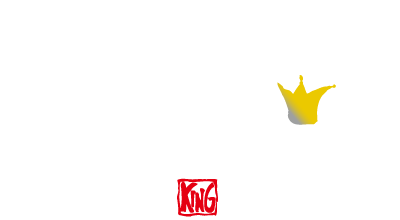飯田橋でおいしいお好み焼き・もんじゃ焼き・鉄板焼きをお探しでしたら居酒屋 お好みキングをご検討ください。もんじゃ焼きはお好み焼きと異なり水分の量が多く、先に調味料を混ぜて味付けしている点が特徴です。パリッとした香ばしい食感が楽しめ、様々な年代の人から愛されています。鉄板焼き屋や居酒屋などでも定番のもんじゃ焼きですが、そのルーツなどを知っている方はあまり多くないはずです。
こちらでは、もんじゃ焼きの魅力と作り方、由来・歴史などを紹介いたします。
もんじゃ焼きの魅力と作り方を紹介
もんじゃ焼きは一口分を小さなコテで取って食べるのが特徴で、鉄板に押し付けて焦げ目をつけて食べていきます。そのため、パリッとした食感やトロッとした食感など、様々な食感を同時に味わえる点が魅力です。焦がし具合も調整でき、好みに合わせて食べ進めることができます。
もんじゃ焼きは、お店によって自分で焼くパターンと店員が焼くパターンがあります。こちらでは、一般的なもんじゃ焼きの作り方を紹介するので、ぜひ参考になさってください。
準備
まずは具材を切って、生地と一緒に器に入れます。具材はキャベツ・天かす・イカ・餅などが定番です。
具材を焼く
生地は器の中に残し、先に具材だけ焼いていきます。キャベツがしんなりしてきたタイミングで、コテを使って具材を細かくしながら炒めていきます。
土手を作って生地を流し込む
炒めた具材をドーナツ状にして、土手を作っていきます。次に器に残しておいた生地を、土手の中に流し込みます。土手から出ないように、ゆっくり流し込むのがポイントです。
仕上げ
生地に火が通っていくにつれて蒸発していくので、少しずつ土手を広げていき、好みのタイミングで具材と生地を混ぜます。全体に火が通ったら、外側からコテで少しずつ食べていきましょう。
もんじゃ焼きは土手がおいしくする!飲み放題と一緒に楽しもう
もんじゃ焼きの焼き方には浅草流と月島流があります。ポピュラーなのはダムのように丸く土手を作り生地を流し込む月島流です。
もんじゃで土手を作る理由はお好み焼きと比べて生地の水分が多いからです。サラっとしているため具材と絡みにくく、フチのない鉄板だと広がりすぎてしまいます。具材を炒めてから生地を流し込むときに、土手からはみ出ないようにすると上手に焼けます。
もんじゃを焼くコツ すき間NG
できるだけすき間がうまれないように土手を作りましょう。炒めた具材をできるだけ近くに寄せて密着させるのと少し高さを持たせるのがコツです。
生地は一気に入れない
生地を一気に入れるとあふれでてしまうので、何回かに分けて流し込みましょう。1度入れた生地にとろみが出てきたら、追加するタイミングです。かき混ぜすぎると土手からもれてしまうこともあるので要注意です。
生地がとろっとしてくるまでは放置していても構いません。食前酒を楽しみながら生地がぐつぐつと煮えていく様子も鉄板焼きでもんじゃを楽しむ醍醐味の1つです。鉄板焼き居酒屋 お好みキングは飲み放題メニューも豊富なので、お好きなお酒とともにもんじゃができあがるまでの時間をお楽しみください。
もんじゃ焼きをおいしく食べる一工夫
もんじゃ焼きは、小さなコテで端のほうから一口分をはがして食べるのが基本的な食べ方です。その際は、おこげも一緒に鉄板からはがすように取るのがコツです。生地のトロっとした食感とともに、鉄板に触れる部分のカリっとしたおこげを味わえるのも、もんじゃ焼きの醍醐味といえます。
一口分はがし取ったもんじゃ焼きは、鉄板に一度押し付けて好みの焼け具合に調整し、アツアツの状態で口へと運び入れましょう。少しずつ焦げ目をつけて食べることで、より香ばしくおいしさが増します。
コテを持ったら、もんじゃ焼きを鉄板に押し付けるように手前に引き寄せます。力をグッと入れることでいい具合に焦げ目がつき、コテの先端部分に生地がくっついて食べやすくなります。居酒屋などでもんじゃ焼きを食べる際は、ぜひ試してみてください。
もんじゃの食べ方のポイント
ちょっとした工夫でもんじゃのおいしさが変わってきますので、ぜひ試してみてください。
好きなトッピングを乗せる
居酒屋や鉄板焼き店などでもんじゃ焼きを食べる際、基本メニューのほかに、お好みの具材を乗せることができます。もんじゃ焼きで定番のトッピングといえば、お好み焼きのメニューにもある豚バラ・イカ・エビのほか、ベビースターラーメン・チーズ・揚げ玉(天カス)・干しエビ(桜エビ)・餅・明太子・納豆・キムチなどです。最近では、トマトや梅干し、大葉、カレー粉などの変わり種も人気があります。
ヘラを上手に使っておこげを作る
もんじゃ焼きの通の食べ方は、もんじゃ焼き用の小さなヘラを使って、鉄板に押し付けておこげを作ることです。焦がしながら食べることでより香ばしさが増しておいしくなります。
もんじゃ焼きの名前の由来
もんじゃ焼きは子供のおやつや、大人のおつまみとして、幅広い世代に愛されている粉もの料理です。今ではもんじゃ焼きの名前で定着していますが、最初は「もんじやき(文字焼き)」と呼ばれていて、それが訛って「もんじゃ焼き」になったといわれています。
「もんじやき(文字焼き)」は、江戸時代末期から明治時代の物資が不足していた時代に、小麦粉を水で溶いて鉄板に文字を書いて子供に教えたり、遊んだりしていたことから、その名前になったとされています。そこから「もんじ」が「もんじゃ」になり、今のもんじゃ焼きとして定着したのです。
もんじゃ焼きの歴史
もんじゃ焼きは東京が発祥で、お好み焼きよりも歴史が古いといわれています。昭和20年代頃から現在のようなスタイルになっていて、食事というよりは駄菓子として親しまれていました。現代では、もんじゃ焼きはお好み焼き屋や居酒屋などで大人が食べるイメージがありますが、昔は駄菓子屋に鉄板があり、子供達がおやつとして食べていたのです。
駄菓子屋で人気だった理由は、戦後で物資が不足していたことが関係します。その頃のもんじゃ焼きは、小麦粉やうどん粉を水で溶いて、ソースや醤油で味付けしただけのシンプルなものでした。特別な材料がなくても、安価でお腹を膨らませることができたため、おやつとして人気だったのです。
現代のように様々な具材が入った、食事としてのもんじゃ焼きが定番になったのは、1980年代頃といわれています。餅や明太子、チーズといった様々な具材が入るようになり、主食の一つとして定着しました。
居酒屋でも人気のもんじゃ焼きとお好み焼きの違いは?
もんじゃ焼きとお好み焼きが別物なのは、皆さんご存知かと思います。では、具体的にどういった点が違いとして挙げられるのでしょうか?
もんじゃ焼きとお好み焼きには、以下のような違いがあります。
発祥
まず、もんじゃ焼きとお好み焼きは発祥の地に違いがあります。もんじゃ焼きは東京が発祥で、浅草や月島にも店舗が多く存在しています。
それに対してお好み焼きは、大阪や広島で広まった食べ物です。
それぞれの特徴
もんじゃ焼きとお好み焼きは、具材はほとんど同じです。小麦粉と水をベースに、野菜やお肉などを入れています。もんじゃ焼きの特徴としては、水分量の多さが挙げられます。多めの水で小麦粉を溶き、ソースなどで先に味付けをします。また具材と生地を混ぜずに焼いていくのも、もんじゃ焼きの特徴です。
それに対してお好み焼きは、生地と具材を一緒に混ぜて両面焼くのが特徴です。焼き上がってからソースで味付けする点も違いといえます。
もんじゃ焼きのカロリー・糖質はどのくらい?
居酒屋メニューの中でもお酒のお供として人気の高いもんじゃ焼き。もんじゃ焼きは小麦粉をふんだんに使用した“粉もの”であるため、カロリーや糖質が気になる方もいるでしょう。
もんじゃ焼きのカロリーと糖質は、中に入れる具材によっても変わってきますが、1人前(540g)あたりのカロリーは約500~510kcalで、糖質量は約50~53gが平均値です。ちなみに、お好み焼きのカロリーの平均値/1人前は約540~545kcalで、もんじゃ焼きと大差はありません。
食べすぎには注意が必要ですが、もんじゃ焼きにはたっぷりのキャベツが入り、代表的な具材としてもやしや桜エビ、豚肉、イカ、紅ショウガ、揚げ玉などがあります。
特に多く使用するキャベツには、ビタミンCやビタミンK、ビタミンUやビタミンB6、カリウム、食物繊維など体に必要な栄養素が豊富に含まれており、健康維持や美容の心強い味方になってくれることでしょう。
もんじゃ焼きのおすすめメニューをご紹介
もんじゃ焼きは、組み合わせる素材によってバリエーションが豊富にあります。鉄板居酒屋 お好みキングでは定番もんじゃの他にも、様々なメニューがありますのでご紹介します。
カレーもんじゃ
皆が大好きなカレー味のもんじゃ焼きです。他の具材と組み合わせることで、カレーとはまた違った味わいや食感を楽しめます。
しそもんじゃ
しそをトッピングした新感覚のもんじゃ焼きです。しその爽やかな風味が加わり、さっぱりといただけます。
海鮮もんじゃ
イカやエビなどの具材たっぷりで、海鮮の旨味が詰まった食べ応え抜群のもんじゃ焼きです。
明太チーズもんじゃ
もんじゃ焼きで大人気の明太子とチーズは、間違いのない組み合わせです。明太子のプチプチ食感とまろやかなチーズで、やみつき必至のおいしさになります。
おやつからおつまみまで!もんじゃ焼きを食べるおすすめのシーン
外は「カリッ」、中は「とろり」「ふんわり」など様々な食感を同時に味わえる、好みに合わせていろいろなトッピングで楽しめる、トッピングによって幅広い栄養素を手軽に摂取できるなど、もんじゃ焼きには多くの魅力があります。お好み焼きよりも歴史が古いといわれており、子供から大人まで幅広い層に親しまれているもんじゃ焼きは、おやつから主食、お酒のおつまみなど幅広いシーンで大人気です。
小麦粉を水で溶いたシンプルな味は、軽食に適していることからおやつやおつまみとして重宝します。また、トッピングを盛り沢山にすれば主食にもなり、どんなシーンにも最適です。
おこげのカリカリと香ばしさ、そしてとろりとした食感が魅力のもんじゃ焼きを、おやつや主食、お酒のおつまみとしてぜひお楽しみください。
飯田橋駅・水道橋駅近くの鉄板焼き居酒屋・お好みキングでは、お好み焼きやもんじゃ焼き、ステーキなど鉄板焼きをメインに提供しています。普段のランチ・ディナーはもちろん、友人や同僚との飲み会、大人数での宴会など幅広いシーンでご利用いただけます。
鉄板焼きといえばお好み焼きともんじゃ焼き!鉄板焼きが楽しい・おいしい理由
居酒屋で食べる鉄板焼きの代表的なメニューとして、ステーキや卵料理、各種野菜焼きのほか、お好み焼き・もんじゃ焼きがあります。幅広い層に人気の高い鉄板焼きにはどのような魅力があるのでしょうか。
でき上がるまでの工程を楽しめる
鉄板焼きの大きな魅力は、でき上がるまでの工程を楽しめることです。作る人の手さばきを間近で見ることで、料理の変化を追いながらワクワク感が高まります。
手軽に楽しめる
食材や具材を鉄板の上で焼くだけで完成するため、手軽に楽しめるのも鉄板焼きの魅力です。特にお好み焼きやもんじゃ焼きは複数人で分けて食べることができ、料理を一緒に囲めるのも楽しさの一つでしょう。
視覚・聴覚・嗅覚・味覚からおいしさを実感できる
鉄板焼きは、味覚だけでなく、直接目の前で視覚・聴覚・嗅覚も実感できます。香ばしい匂いやジューっという焼く音、そして食材が目の前で焼き上げられる様子は、より一層食事を楽しませてくれます。
パフォーマンスを楽しめる
鉄板焼きはエンターテインメント性の高い調理法です。作る人の技術やパフォーマンスを楽しみながら、食事を楽しむことができます。
高揚感・迫力
鉄板焼きの魅力は、焼いているときの音や見た目の迫力にもあります。新鮮な魚介やジューシーなお肉が焼ける瞬間の音、パチパチグツグツと仕上がっていくビジュアルは、より食欲をそそられることでしょう。
飯田橋で楽しむお好み焼き:鉄板焼きの魅力とおいしい食べ方のコツ
鉄板焼きの魅力は、その場で調理が進む様子を楽しめる点にありますが、特にお好み焼きには独自のこだわりがあります。飯田橋にある鉄板焼き店では、シンプルな定番メニューから創作系まで幅広い種類のお好み焼きを楽しむことができます。
まず、お好み焼きの基本的な作り方についてご紹介します。生地は小麦粉をベースに、出汁や山芋を加えてふっくらと仕上げます。具材としては、キャベツ、豚肉、イカ、エビ、そしてチーズや明太子など、お好みで選べるのが楽しいポイントです。これらの具材を均等に混ぜ合わせ、鉄板の上でじっくりと焼き上げます。
焼き上がりのポイントは、外側がカリッと、中がふんわりと仕上がることです。鉄板の温度管理が重要で、高温で一気に焼き上げることで、香ばしい風味が引き立ちます。また、ソースやマヨネーズ、鰹節、青のりなどのトッピングも、お好みに合わせて調整できます。これらのトッピングが一体となり、お好み焼きの味わいを一層引き立てます。
鉄板焼き店では、店内で焼かれる様子を見ながら食べることで、視覚的にも楽しむことができます。
さらに、お好み焼きをおいしく食べるコツとして、焼き加減を自分で調整する方法があります。鉄板の上で自分で焼くスタイルのお店では、好みの焼き加減に合わせて、外側をカリッと焼き上げることが可能です。特に、少し焦げ目がつくくらいが香ばしくておいしいです。
最後に、お好み焼きはお酒との相性も抜群です。特にビールやハイボールと一緒に楽しむと、その旨味が一層引き立ちます。飯田橋の鉄板焼き店では、豊富なドリンクメニューも揃っており、食事と一緒にお酒も楽しめる点が魅力です。
鉄板焼きの魅力を存分に楽しむために、ぜひ飯田橋のお店でおいしいお好み焼きを堪能してみてください。
お好み焼き・もんじゃ焼きなど鉄板焼きを居酒屋で楽しむなら

もんじゃ焼きは、今でこそ鉄板焼き屋や居酒屋で親しまれているイメージがありますが、昔は駄菓子屋で子供のおやつとして食べられていました。お好み焼きと違い東京が発祥で、現在にいたるまで幅広い世代の方々に愛されてきたのです。
もんじゃ焼きやお好み焼きのお店をお探しなら、ぜひお好みキングへご来店ください。お好みキングは、飯田橋駅・水道橋駅近くで営業する鉄板焼き居酒屋です。
こだわりのお好み焼きをはじめ、おつまみにぴったりなもんじゃ焼き、ステーキなど鉄板焼きメニューも豊富に取り揃えています。飲み放題や宴会メニューも用意しているので、お一人様から団体様まで、お気軽にご利用ください。
もんじゃ焼き・お好み焼きに関するお役立ちコラム
飯田橋駅近く!お好み焼き・もんじゃ焼きなら鉄板居酒屋 お好みキング
- 店名
- 鉄板居酒屋 お好みキング
- 運営会社
- 株式会社 A-feel
- 住所
- 〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-3-9 VERDAビル1F - TEL
- 03-6261‐6161
- FAX
- 03-6261-6164
- アクセス
- 地下鉄飯田橋駅A5番出口徒歩30秒
JR中央線飯田橋駅徒歩4分
都営大江戸線飯田橋駅徒歩4分
地下鉄九段下駅徒歩10分 - 営業時間
- ランチ[月~金]
11:30~14:00(料理L.O. 13:30)
ディナー[月~土]
17:00~23:00(料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:30)
状況に応じて変更あり
電子タバコ可 - 席紹介
- カウンター席 8席
テーブル席 27席
半個室対応可(10席)
貸切 25名~40名 - 駐車場
- なし
近くにコインパーキングあり - URL
- https://okonomi-king.com/